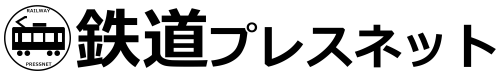東京メトロ有楽町線の分岐線が具体化に向けて動き出した。昨年2022年3月、東京メトロが分岐線の「根元」部分になる豊洲~住吉4.8kmの第1種鉄道事業許可を取得。現在は本格的な着工に向けた準備が進められている。

構想では千葉県野田市まで延伸することが考えられており、つくばエクスプレス線の直通化を前提とした八潮~野田市の部分整備も地元で検討されている。これに加えて近年は茨城県西南部への延伸を求める動きがあり、坂東市や下妻市など西南部の自治体が国への要望活動を行っている。

野田市までの延伸だけでも膨大な費用がかかることは確実で、茨城への延伸も実現できるかどうかは不透明だ。しかも、茨城への延伸となれば「地磁気観測所」の存在も大きな障壁になる。2022年12月から今年2023年1月にかけ、毎日新聞などがこの課題を取り上げて注目された。
電化路線が地磁気の観測に悪影響
地磁気観測所は気象庁の観測施設。筑波山頂から東へ約7kmの茨城県石岡市柿岡地区にある。その名の通り自然発生的な地球磁気(地磁気)の観測を行っており、観測に際しては人為的に作り出された電気をできるだけ遠ざける必要がある。

電化された鉄道の場合、電流は変電所から架線やパンタグラフ、モーターを経てレールに流れるが、その一部は地面に漏れて広がる。この漏れた電流が雑音となる磁場を地下で作り出し、地磁気の観測を難しくしてしまう。電化路線の電気は直流と交流の2種類あるが、とくに直流電気は広範囲に広がりやすく、地磁気観測への影響が大きい。
このため、電気事業法の下位省令「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技省令)では、「直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない」(第43条)と定めている。
電技省令は直流の電線路などをどのように「施設」すればいいのかは定めていない。経済産業省の商務情報政策局は取材に対し「具体的な条件を示した法令や告示などは存在しないものと認識している」と話し、電化路線を整備する場合は個別に判断するという考え方だ。
その一方、地磁気観測所は「直流方式で運行される電車では、地磁気観測への影響が35km程度にまで及びます」との見解を公表している。地磁気観測所から半径35km程度の範囲では「観測上の障害を及ぼさないように施設」しない限り、直流電化路線を整備することは難しい。
実際は35kmより若干狭い半径30kmの範囲が直流電化の事実上の制限区域になっており、JR東日本の常磐線は取手以北で交流電化を採用。水戸線も小山駅から数kmまでの地点を除き交流電化されている。2005年に開業したつくばエクスプレス線は守谷以北を交流方式で電化した。

直流電化は送電時に電気が減りやすく(送電ロス)、変電所を多く設ける必要があるため、地上施設の整備コストが高くなりやすい。しかし電車の構造はシンプルにできるため、導入コストが安いという利点がある。逆に交流電化は送電ロスが少なく変電所を少なくでき、地上施設の整備コストは安いが、電車は複雑な構造になるため導入コストは高い。利用者が非常に多く車両を大量に導入しなければならない大都市圏の通勤鉄道なら、直流電化のほうがコストパフォーマンスがいいといえる。
東京圏の通勤路線で電車が大量に必要な常磐線やつくばエクスプレスにしても、本来なら全線を直流電化したほうがコストを抑えられる。しかし近くに地磁気観測所があるため、コストの増減に関係なく交流電化しなければならないという事情がある。
有楽町線を茨城県西南部に延伸する場合、坂東市はともかく、その先の下妻市などは「30km圏」に入るため、基本的には交流電化を採用するしかない。現在の有楽町線は直流電化で電車もすべて直流タイプだから、茨城に延伸するなら交流方式で整備し、交直両用の電車も新たに導入する必要がある。全線直流電化で整備する場合に比べコストがかさむ。
今後、有楽町線の茨城延伸が本格的に検討されるようなことが本当にあれば、この問題が足かせになるのは確実だろう。
距離は「必須の要件ではない」
ただ、電技省令の第43条は「観測上の障害を及ぼさないように施設」できるなら直流方式で電化することも可能、とも読める。経産省の商務情報政策局も「(地磁気観測所から)30km離すということは必須の要件ではないと認識している」と話した。
実際、過去には直流電化の鉄道が「30km圏」内に存在した。現在の水戸市を中心としたエリアでは茨城交通の水浜線が1922年に直流方式で開業し、同社の茨城線も一部の区間が1944~1945年に直流電化された。現在の土浦市のエリアでは常南電気鉄道が1926年に開業している。いずれも地磁気観測所が現在地に移転(1912年)したあとのことだ。

現在、直流電化路線の多くは電圧が1500Vだが、これらの路線は直流600Vと電圧が低かった。また、一部の路線では架線を2本設置した「複線式」を採用。本来はレールに流す電流をもう一本の架線に流すことで地面に漏れないようにした。日本ではあまり見かけなくなったがトロリーバスと同じ方式だ。このような工夫を行えば直流電化でも「観測上の障害」を抑えることができるといえる。
ただ、低電圧や複線式による電化は高速運転が難しいなどのデメリットもあった。さらに「30km圏」の直流電化路線は利用者の減少もあり、常南電気鉄道は開業からわずか12年後の1938年に廃止。茨城交通の茨城線は1965年に電車運転を終了して1971年までに全線廃止され、水浜線も1966年までに全線廃止された。
「特殊な直流電化」検討したが…
ちなみに、常磐線の取手駅から北上して水戸線の下館駅を結ぶ関東鉄道の常総線も大半が「30km圏」に含まれるため、全線が非電化だ。ただ、東京圏の通勤路線のため1970年代には抜本的な輸送力の増強が必要になり、1977~1984年にかけ一部の区間(取手~水海道)のみ複線化。さらに電化も何度か検討されている。

先に述べた通り交流電車の導入コストは直流電車に比べ割高で、中小私鉄がおいそれと導入できるものではない。そこで一時期検討されたのが、特殊な方式による直流電化だった。これは通電区間を数kmごとに細かく分割することで、地面に漏れる電流の範囲を抑えるというものだった。
1994年に関東鉄道が沿線自治体に示した試算では、交流電化に240億円かかるのに対して直流電化は305億円で、60億円ほど高い。交流電車より安い直流電車の導入で増額分を相殺できるかどうか、微妙なところだろう。
同社は2004年にも交流電化費用の試算を沿線自治体に示しているが、施設の整備だけでも258億円かかるとした。いずれにせよ、年間の営業利益がコロナ禍前でも10億円台の関東鉄道には手に余るプロジェクトで、国や自治体からの公的支援がなければ電化は難しそうだ。
※加筆しました(2023年3月23日7時32分)。
《関連記事》
・東京メトロ有楽町線「野田・茨城延伸」関係自治体など早期実現を国交相に要望
・東京都の臨海地下鉄「羽田空港接続」も検討へ 事業計画案を公表、6km・7駅を整備